皆様、こんにちは!突然ですが、「論語」という言葉は聞いたことがありますか?
・「何か難しそうな古典ですよね?」
・「孔子?学校で習ったような…」
と思われたそこのあなた。はい、まさにその通りです。
正直なところ、ボク自身も学生時代は「ふーん」という程度で、深く理解しておりませんでした。
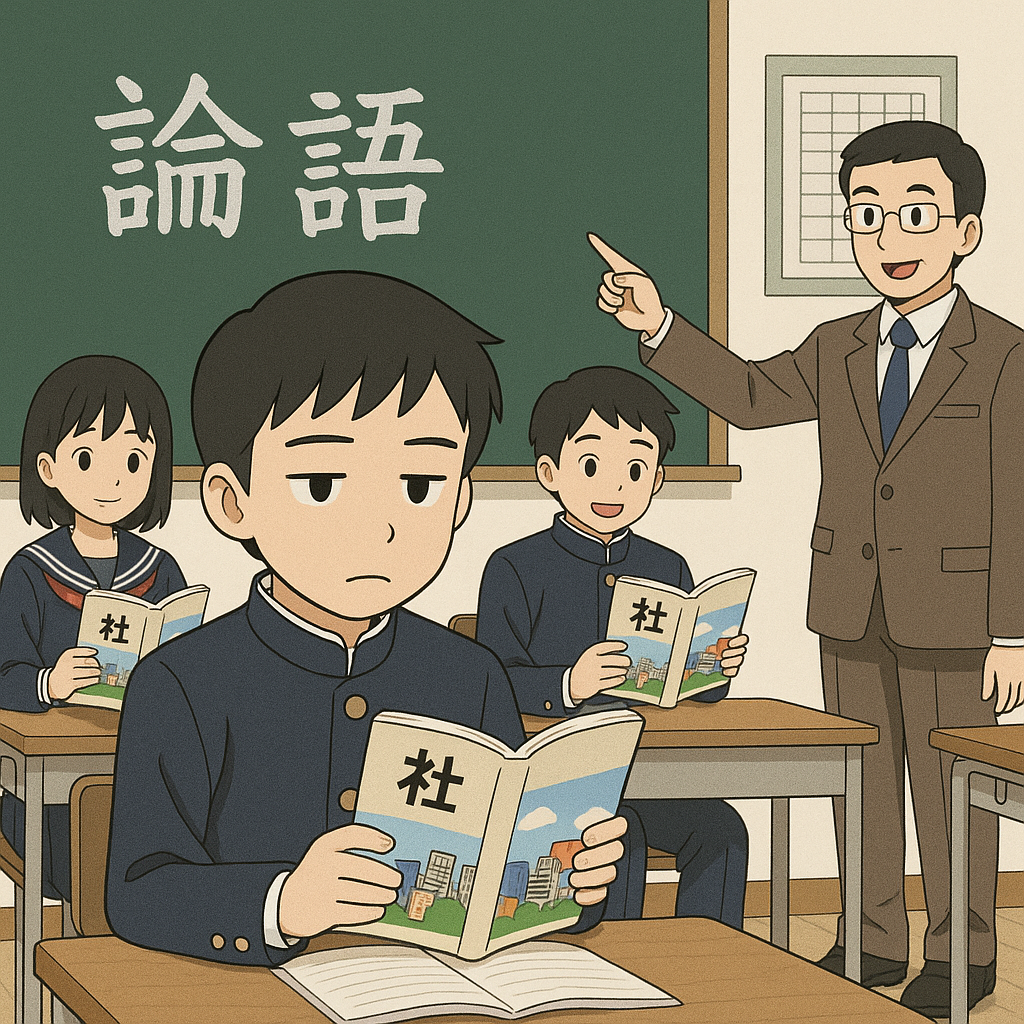
しかしながら、最近改めてこの『論語』を読んでみたところ、これが非常に面白く、そして現在の私たちの悩みや疑問に対し、まさに的確な答えを与えてくれているのではないか、という発見がありました。
例えば、
・「どうすればもっと人間関係を円滑にできるのだろうか?」
・「仕事で壁にぶつかった時、どのように乗り越えれば良いのだろう?」
・「そもそも、自分はどのように生きていけば良いのだろう?」
といった漠然とした悩みに、孔子先生がシンプルかつ奥深い言葉で、スッと光を当ててくださいます。
まるで、ずっと探していた答えを、タイムカプセルの中から見つけたような感覚です。
「論語」とは、今から約2500年も前の中国で活躍された、孔子(こうし)という非常に優れた思想家と、その弟子たちとの対話をまとめたものです。
例えるならば、孔子先生の「名言集」であり、弟子たちとの「Q&A集」のようなものです。
この記事では、「読みたいけど、なかなか手が出ない」「聞いたことはあるけど、詳しくは知らない」「孔子ってどんな人?」という方に向けて、改めて知るきっかけになるような構成でお届けします!
孔子の想いや背景、他の読者の感想も踏まえてご紹介 します!
難しく考える必要はありません。カフェで友人と語らうような感覚で、ぜひ昔の偉人の言葉に触れてみてください。
きっと、皆様の明日を少しだけ豊かにするヒントが見つかるはずです !
孔子とはどんな人物 ?
● 釈迦(しゃか)・キリスト・ソクラテスに並び四聖人
● 何よりも道徳を重んじた人。
● 現在でも使われる「温故知新(おんこちしん)」や「付和雷同(ふわらいどう)」を遺した人物
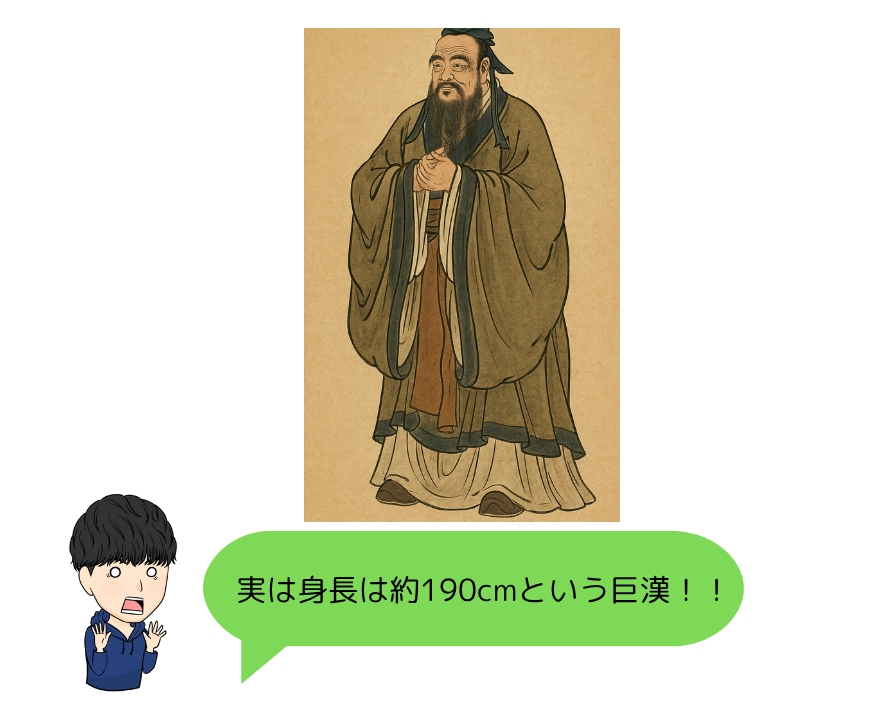
孔子の幼少期は決して恵まれていませんでした。3歳の時に父を、17歳頃には母を亡くし、貧しい生活を送ることになります。
しかし、彼は幼い頃から祭礼の真似事をするなど、礼儀作法や古典に対し並々ならぬ関心と好奇心を示しました。
独学で礼・音楽・歴史・詩文などの古典に没頭し、その才能と努力で徐々に頭角を現していきます。
成人後は、魯(ろ)の国の下級役人としてキャリアをスタートさせ、倉庫管理や牧場管理といった職を経て、司法や外交にも関わる高官にまで昇進します。
しかし、自身の理想とする政治が実現できないことに限界を感じ、官職を辞してしまいます。
その後、約14年間にわたり諸国を巡り(これを「諸国遍歴」と呼びます)、各国の君主や為政者(いせいしゃ)に自らの理想の政治や社会のあり方を説きましたが、なかなか受け入れられませんでした。
68歳頃に故郷の魯に戻ってからは、政治に直接関わることはせず、古典の整理や編纂、そして何よりも多くの弟子たちの教育に生涯を捧げました。
弟子は生涯で3,000人にも上ると言われ、その中から多くの有能な人材を輩出しました。
簡潔に言えば、孔子は、貧しい生い立ちの中で学問の道を究め、乱世を憂い、人々の心のあり方や社会の秩序を回復するために、生涯をかけて「仁」「礼」「義」といった普遍的な道徳を説き、多くの弟子を育成した偉大な教育者・思想家でした。
孔子が重要視した仁・義・礼・智・信
「仁義礼智信(じんぎれいちしん)」は、儒教における人間が持つべき基本的な五つの徳目です。
これらは「五常(ごじょう)」とも呼ばれ、人が社会生活を送る上で大切にすべき道徳的な価値観を示しています。皆さんに備わっている道徳観の根幹は五常にあります。
仁(じん)
他人への思いやりや慈しみの心です。自分と他人を区別せず、全ての人を愛し、大切に思う気持ちを指します。
孔子が最も重視した徳目であり、「己の欲せざるところ、人に施すことなかれ」(自分がされたくないことは、他人にもしてはいけない)という言葉に代表されます。
2. 義(ぎ)
人として行うべき正しい行いや道理に従う心です。私利私欲にとらわれず、公正で適切な判断を下し、行動することを意味します。「正しいこと」を追求し、不正を許さない姿勢です。
3. 礼(れい)
社会の秩序を保ち、人と人との関係を円滑にするための規範や作法です。単なる形式だけでなく、相手を尊重し、敬意を表す心が伴うことが重要だとされます。
社会生活におけるルールやマナーの基礎となります。
4. 智(ち)
物事を正しく見極め、判断する知恵や道理を理解する能力です。単なる知識だけでなく、善悪を判断し、適切な行動を選択する実践的な知恵を指します。
5. 信(しん)
誠実さや信頼性です。嘘をつかず、約束を守り、真心を尽くすことで、人からの信頼を得ることを意味します。人と人との関係の基本であり、社会を成り立たせる上で不可欠な要素です。
いつ、どうやって書かれたのか?
今から約2500年前、中国の春秋時代に孔子と弟子との対話形式で編纂(へんさん)された経典です。孔子は数多くの弟子が存在し、弟子によって解釈にも違いがありました。
ねじれを生まないためにも、孔子の言葉をそのままに残しましたものが『論語』となりました。(のちの儒教の原型)
彼は、知識を教えるだけでなく、一人ひとりの人格形成を重視し、弟子それぞれの個性や特性に応じて教え方を変えるなど、熱心に指導しました。
江戸時代(徳川幕府)に儒教を改良した朱子学が統治理念として採用し、国家の正式な学問として重視しました。
朱子学はよく耳にする武士道のお手本ともなっています。

この頃に、朱子学が広まり、現在の日本人の無意識に身についている道徳観になっているのでしょう。
なぜ書かれたのか ?
孔子が生きた紀元前6〜5世紀の中国(春秋時代)は、各地の諸侯(小国の君主)が互いに争い、中央の周王朝の権威は形だけになり、社会秩序や道徳が崩れつつある混乱の時代でした。
このような不安定な社会の中で、孔子は以下のように考えました。
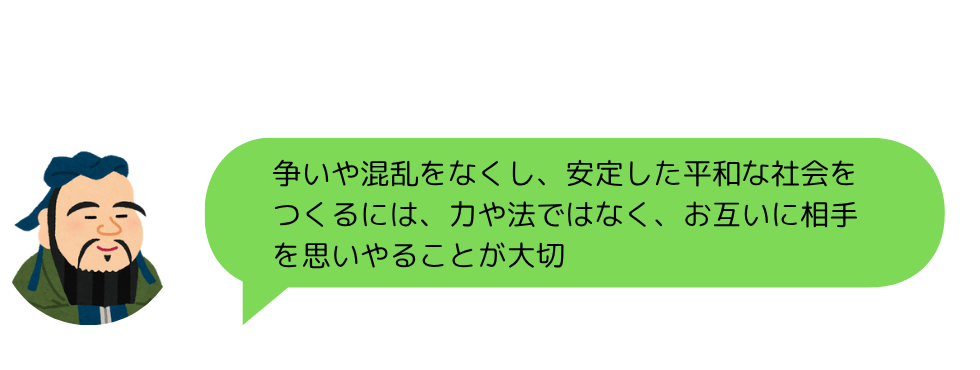
そのために、人間関係の中で徳を重んじ、社会秩序や道徳を築くことを重視しています。孔子は、これらの徳目を身につけた「君子(くんし)」を理想とし、個人の修養こそが社会全体の秩序と調和につながると考えました。
儒教は一人ひとりが「君子」になるのが理想。孔子の最終的な目標は、「君子が率いる秩序ある世界」です。
(君子とは、道徳的に優れ、思いやりと知恵を持って行動する人)吹き出し
本書の感想
思いやりの大切さ、効力をを改めて思い出すことができる一冊。『論語』の教えを軸として今日まで生きてきたのだと実感しました。
まさに、日本・アジアの「道徳」の原型。無意識に備わっている「道徳観」は『論語』のものでしょう。人としての姿勢(心持ち)や謙虚さ、思いやりの精神は本書が発祥に感じます。
論語は数多くの弟子を輩出しているので、多彩な形で昨今まで語り継がれているのだと推測します。
比較的、短い文章で記されているので、解釈の仕方も多種多様。 そう考えると、孔子の影響力は驚異的。
読書メーターによる読者の感想
今回は、『論語 金沢 治 訳注 岩波文庫 青202‐1』を参考にします。400件以上の中から様々な読者の感想をまとめてみました!
読む前から聞いたことのある言葉もあれば、読んでみて初めて知って、深く納得させられた言葉もあった。
当時と今で、社会も人間も全く違うはずなのに、孔子の言葉は普遍的で、今聞いても気付かされるものだった。
儒教道徳や格言集の類と身構えることなく、人としての日々の生き方を記したものとして比較的気楽に読むことができるのはやはり魅力的 。
文章が細切れなので通勤時間に便利。訳も学校で習ったほど文語っぽくなくていい感じでした。
ひたすら堅い説教臭いというわけではなくて、孔子や弟子たちの人間臭い感じも伝わってきて、ほんわかと面白い感じがした。
他の本や学校や会社、社会で様々な形で言われていることをたどると、論語に行き着く。人間として何を規範として生きていくべきか。
繰り返し繰り返し、徳が大事と語られる。時々、孔子も間違ったことをして弟子に指摘されているシーンもあり、孔子の人間臭さが感じられて、教えにとても共感できた。
何度も立ち返って死ぬまで実践していきたい本。
数千年前から受け継がれてきた人類の財産。 現代生活の役に立つかどうかという視点ではなく、人類が経てきた道を顧みるという意味で読み返してみたい。
文化や歴史を受け継げるというのはまさに人間が人間たる最高の贅沢だと思う。
人気の名言とその意味
読書メーターの感想の中でも、人気のあった名言を集めました。その言葉と意味を簡潔にまとめました!(一部省略します)
巧言令色、鮮(すくな)し仁
→口だけ上手で、まわりにいい顔をしていても、徳はない。八方美人は人間関係の本質ではない。
過ちても改めざる、是れを過ちと謂(い)う
→過ちをしても改めない、これが本当の過ち。 問題点を反省し、次の行動の改善に努めよう。
人の己を知らざることを患(うれ)えず、人を知らざることを患う
→人間関係やSNSなどで自分だけを見てもらうことを考えるのではなく、他人を知ることに心がける。そうすると、視野も人脈も広がるということでしょう。
君子は諸(こ)れを己に求む。小人は諸れを人に求む
→君子は自分に”反省して”求めるが小人は他人に求める。自分の責任は自分で受け持つ。 他人に依存し、責任転嫁への否定。
これを知るものはこれを好むものに如(し)かず、これを好むものはこれを楽しむものに如かず
→物事を知っているだけの人は、好む人には及ばない。物事を好んでいるだけの人は、楽しむ人には勝てない。仕事や勉強、趣味も楽しんでしている人は成長が早いということでしょう。
君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
→付和雷同の由来となっている。互いに釣り合いのとれた関係を築き、相手の意見に流されないことを説いています。
「子、四を断つ。意なく、必なく、固なく、我なし。」勝手な心を持たず、無理おしをせず、執着をせず、我を張らない。
・「意(い)なし」:独断や思い込みにとらわれない。事実や道理に基づく態度をとる。
・「必(ひつ)なし」:「必ずこうだ」と決めつけない柔軟な心を持つ。
・「固(こ)なし」:頑固で変化を拒むのではなく、状況や正義に応じて態度を変えることができる。
・「我(が)なし」:自分本位の考えに固執しない。謙虚で他者や全体を尊重する。
『論語』で現代の問題 を解決!
約2500年前の教えが現代の問題を解決する力を持っています。まるで、今を予言していたかのようなお言葉です!
SNS時代での人間関係の築き方
現代社会では、多様な価値観の中で人間関係の構築や維持に悩む人が少なくありません。SNSの普及により、情報過多や誹謗中傷、リアルな人間関係の希薄化なども目立ちます。
「郷人(きょうじん)皆なこれを好(よみ)せば何如(いかん)。子曰く、未だ可(か)ならざるなり。郷人の善き者これを好し、其の善からざる者はこれを悪(にく)まんには如(し)かざるなり」
皆に好かれることが良いこととは限らない、と孔子は説きます。良い人には好かれ、悪い人には嫌われる方が良い、という意味です。
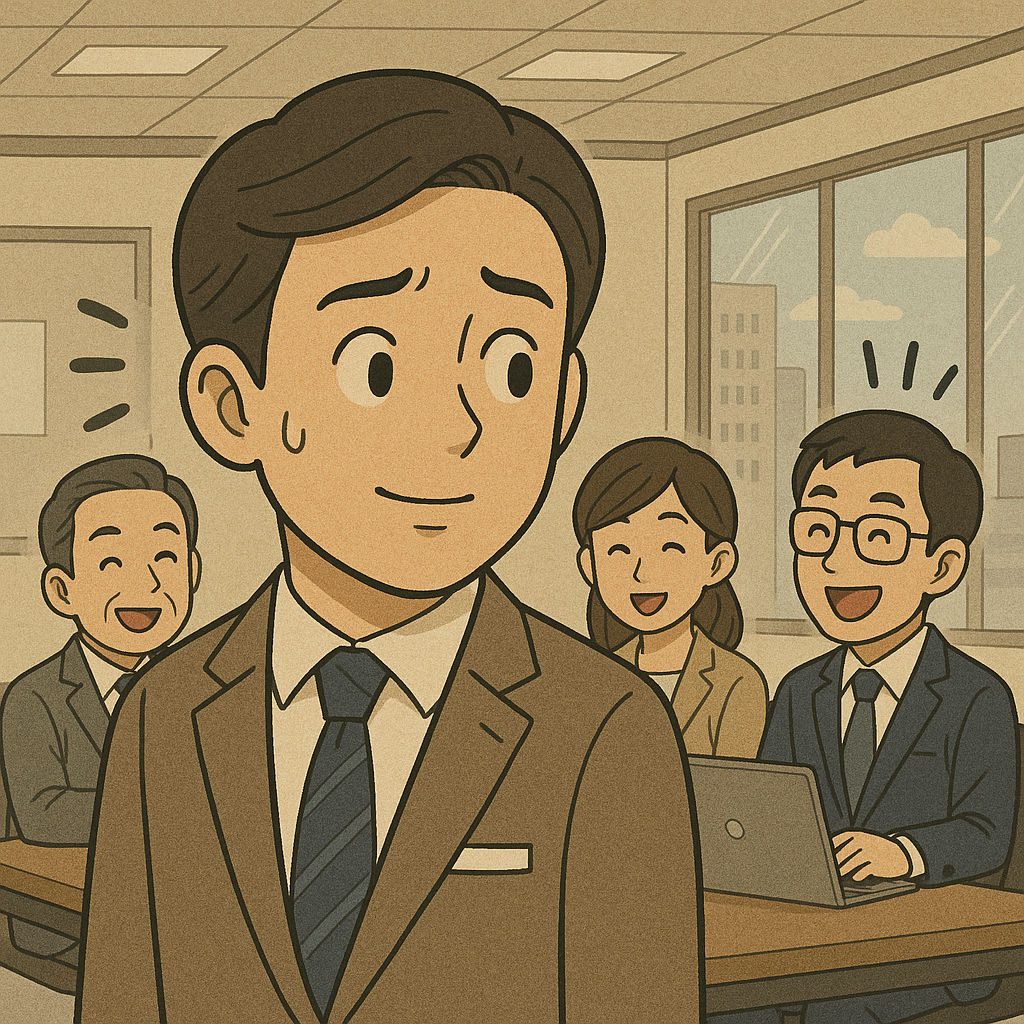
これは、無理に全員に好かれようとせず、自分の信念を持って行動することの重要性を教えてくれます。SNSで「承認欲求」に縛られがちな現代において、自分軸を持つことの大切さを示しています。
まずは知らないことを知る
VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と言われる現代において、仕事やキャリアに関する悩みも尽きません。
これ知ると為(な)し、知らざるを知らずと為せ。是(こ)れ知るなり」
知らないことを知らないと正直に認めることが、真に知るということである、という意味です。
これは、新しい知識やスキルの習得が求められる現代において、謙虚に学び続ける姿勢の重要性を示しています。
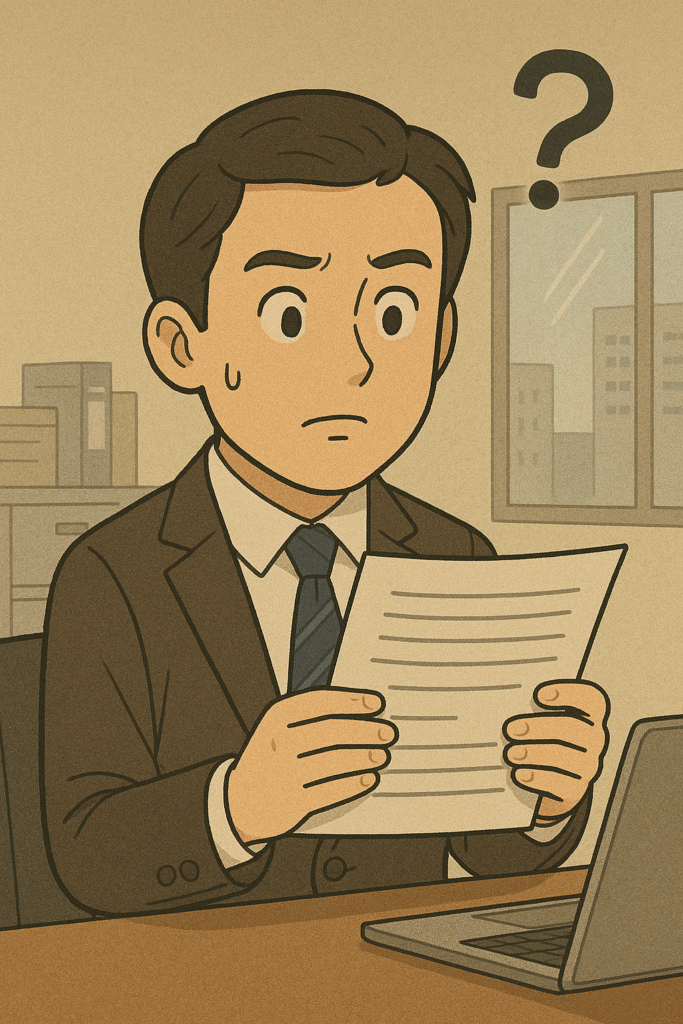
分からないことを隠さず、素直に学ぶ姿勢は、成長の第一歩となります。
情報があふれる現代社会
情報過多な現代において、何が正しく、どう生きるべきか、という根源的な問いに直面する人も多いでしょう。
「学びて思わざれば則(すなわ)ち罔(くら)し、思うて学ばざれば則(すなわ)ち殆(あや)うし」
学ぶばかりで考えなければ知識は身につかず、考えるばかりで学ばなければ危険である、という意味です。これは、情報化社会における情報リテラシーの重要性を示しています。
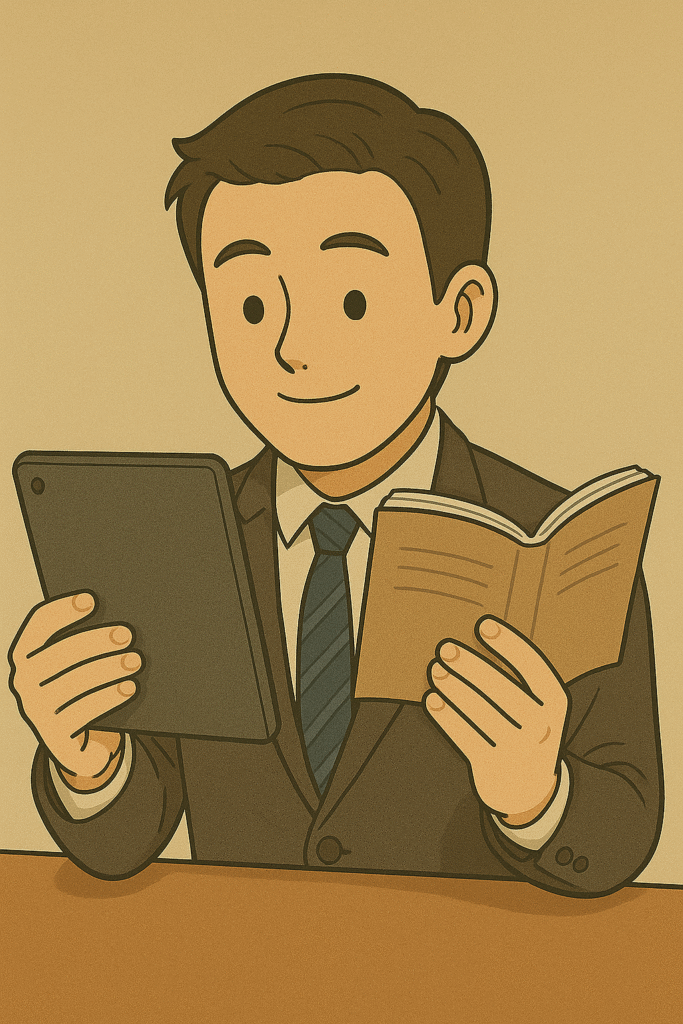
単に情報を鵜呑みにするだけでなく、自ら考え、吟味し、深く考察する力を養うことの重要性を教えてくれます。
まとめ:『論語』は、2500年前から続く「人生の取扱説明書」だった!
ここまで、『論語』がどんな本で、孔子先生がどんな人だったのか、そして意外と今の私たちにも役立つヒントが隠されていることをお伝えしてきました。
正直、「古典」とか「哲学」って聞くと、ちょっと構えちゃう気持ち、めちゃくちゃよくわかります!私もそうでしたから。
でも、今回一緒に見てきたように、『論語』って実は、
・人間関係をスムーズにするヒント
・仕事やキャリアで壁にぶつかった時の乗り越え方
・SNSとの健全な付き合い方自分らしく、芯を持って生きるための道しるべ
のように、ボクたちが日々直面するモヤモヤや悩みに、シンプルだけど奥深い答えをくれる「人生の取扱説明書」みたいなものなんです。
約2500年も前の言葉が、こうして時代を超えて私たちに響くのは、結局のところ、人の悩みや本質って、いつの時代もそんなに変わらないからなのかもしれませんね。
もし、この記事を読んで少しでも「へぇ、論語って面白いかも?」って思ってくれたなら、ぜひ一度、手に取ってみてください。
難しく考えず、パラパラと眺めるだけでも大丈夫です。きっと、あなたの心にストンと落ちる言葉や、ハッと気づかされる考え方に出会えるはずです。
『論語』の言葉が、あなたの毎日をちょっとだけ豊かにするきっかけになったら嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
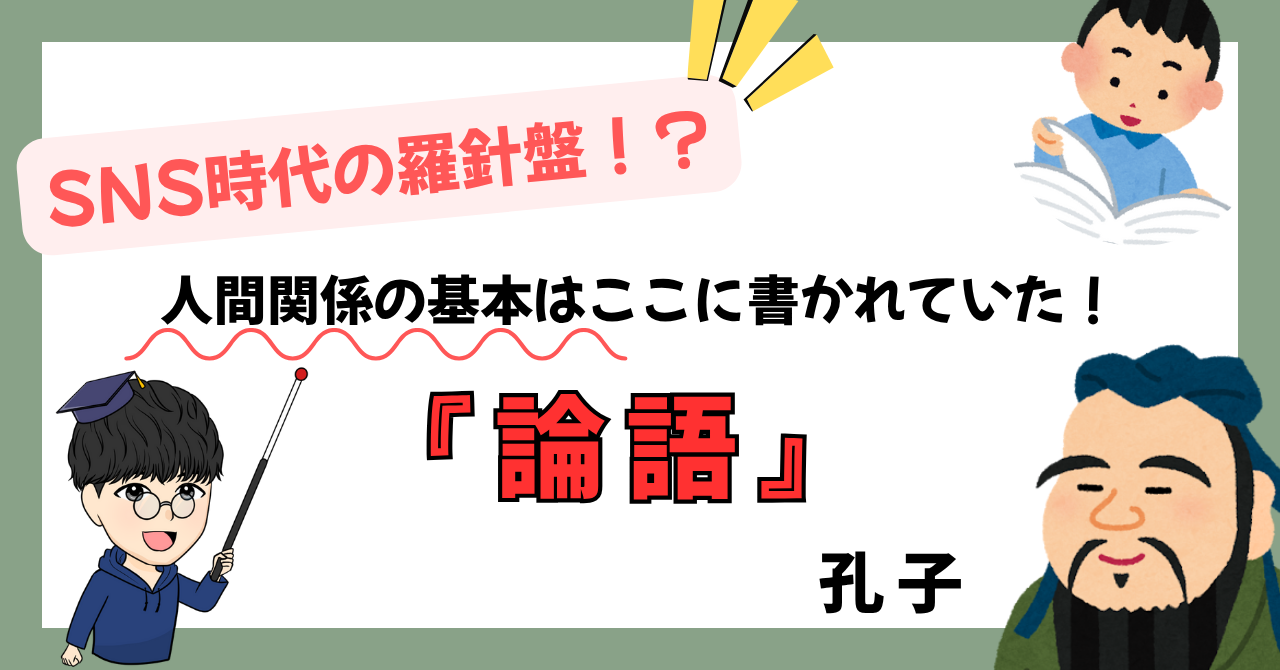
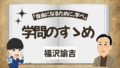
コメント